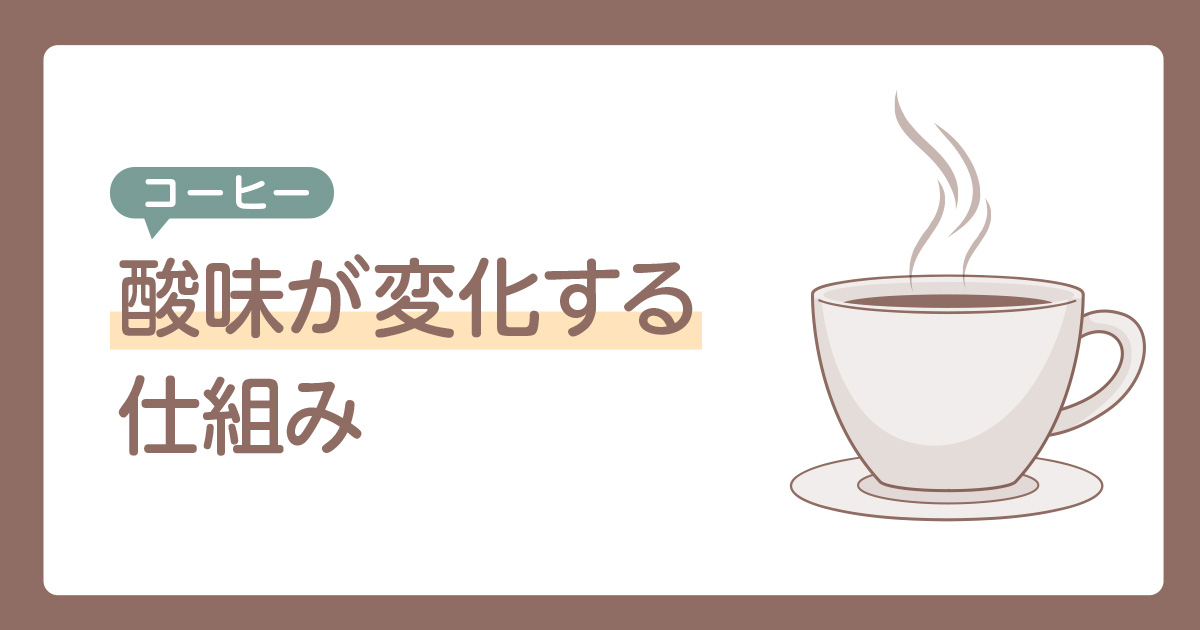皆さんはコーヒーを飲むとき、時々「あれ、このコーヒー、ちょっと酸っぱい?」と感じることはありませんか?
その「酸味」に、少し苦手意識を持っている人もいるかもしれません。実は、私もその一人です。
しかし、このコーヒーの酸味こそが、味わいを豊かにし、コーヒーの個性を際立たせる大切な要素になっています。
ここでは、コーヒーの酸味の成分について解説します。
コーヒーの酸味は1種類から成っているのでなく、何種類もの酸があわさっています。
酸の特性を理解することにより、コーヒー味の変化を楽しめるようになるかもしれません。
コーヒーが持つ様々な酸の種類

コーヒーにはたくさんの種類の酸が含まれていて、それがコーヒーの味の複雑さを作り出しています。
コーヒーに含まれる酸は、主に植物が光合成で作る有機酸という種類に分類されます。
「有機酸」とは、炭素や酸素などの元素で構成される有機化合物の中で、酸性を示すもののことを指します。
代表的なコーヒーに含まれる酸(表1)を見てみましょう。
表1 コーヒーに含まれる代表的な酸
| クエン酸 | レモンやミカンなどの柑橘類に多く含まれている酸。 コーヒーに爽やかな酸味や明るい印象を与えることが多い。 |
|---|---|
| リンゴ酸 | 名前の通りリンゴやブドウに多く含まれる酸で、コーヒーにはまろやかな酸味やフルーティーさをもたらす。 |
| 酢 酸 | お酢の主成分と同じ酸で、コーヒーでは時にシャープな酸味やツンとした印象を与えますが、少量であればフレーバーの一部になることも。 |
| キナ酸 | コーヒーが冷めてくると感じやすくなる、独特の苦味や渋みと関連している。 |
| クロロゲン酸 | コーヒー豆に最も多く含まれる酸。 焙煎される前(生豆の状態)にはたくさん含まれているが、焙煎されると別の成分に変化したり、分解されたりする。 このクロロゲン酸が変化することで、コーヒー特有の苦味や渋み、そしてコクにも影響を与えている。 |
これらの酸がそれぞれ異なるバランスで含まれることで、私たちが感じる様々な「酸味」の表情が生まれます。
ここから、化学的な視点で、それぞれの酸についてご紹介します。
①クエン酸
クエン酸は食べ物だけでなく、掃除用品の1つとして知っている方が多いと思います。
100均でも売っていますよね。
クエン酸の化学式は炭素、酸素、水素のみでできている構造です。
酸の部分である、カルボキシル基COOHが3つある構造をしています。
示性式 C(OH)(CH2COOH)2COOH
融点が153℃、熱分解が175℃、と、常温では固体です。
ただし、OH基やCOOH基がたくさんあるので、水H2Oと親和性が高く、水があるとよく溶けます。
②リンゴ酸
リンゴ酸はあまり知られていませんが、クエン酸と同様に、比較的簡単な構造をとる酸です。
カルボキシル基COOHは2つある構造をとります。
示性式 HOOC-CH(OH)-CH2-COOH
融点130℃なので、こちらも常温で固体です。
特徴的なのが、キラル構造(*補足)をとることです。
(*補足)
キラルとは、同じ成分から成るけど立体構造が違うものを指します。
一般的には、右手と左手の関係と説明されることが多いです。
右手と左手は手のひらをあわせることはできる(成分は同じ)けど、上から重ねあうことはできない(立体構造が違う)ですよね。それが、キラルです。
リンゴ酸も両方の立体構造を持ち、天然では片方だけ、人工的に合成したものは両方を持っています。
両方のキラルが混ざったものを、ラセミ体と言います。
リンゴ酸はラセミ体でも身体に問題ないので、そのまま使われることが多いです。
③酢 酸
お酢と言えば、この成分です。一番簡単な構造をしています。
ちょっとの気温で揮発しやすく、揮発した酢酸によって鼻にツーンときてしまいます。
示性式 CH3COOH
融点16.7℃、沸点118℃なので、常温で液体です。
④クロロゲン酸
コーヒーの特徴的な酸です。最初に紹介したクエン酸や酢酸などとは、全然違う構造をとっているのがわかります。
クロロゲン酸は皆さんも聞いたことのあるポリフェノールと呼ばれる構造で、カフェ酸等とキナ酸のエステル(*補足)です。
ポリフェノールとはカフェ酸の部分のように、ベンゼン環にOH基(フェノール基)が複数(ポリ)結合したものです。
食べ物などに含まれている自然由来のポリフェノールには、様々な効能があり、お茶のカテキンや赤ワインのタンニンも、ポリフェノールに属します。
カフェ酸は、今までの直線的な炭素構造の脂肪族化合物でなく、芳香族化合物(炭素6個が平面上につながった、ベンゼン環を中心とした化合物)と呼ばれる別の種類になります。
クロロゲン酸の融点は207〜209℃です。
(*補足)
エステルとは、カルボキシル基COOHのHのところに炭素などが結合したものです。エステル結合は、カルボン酸とアルコールの脱水反応でできます。
R1-COOH(カルボン酸)+ R2-OH(アルコール)→ R1-COO-R2(エステル)+ H2O
⑤キナ酸
炭素が環状になっている構造にカルボキシル基COOHがくっついています。
単体は結晶性の固体で、融点168°Cです。
OHやCOOHなど、親水性の置換基がいっぱいあるので、水に溶け出しやすいです。
先ほどの、クロロゲン酸の熱分解によって発生します。
つまり、焙煎すればするほど、クロロゲン酸が分解されて、キナ酸ができてくる、ということです。
コーヒーには、さまざまな有機酸が含まれることがわかりましたね。
それでは、コーヒーの酸味に影響を要素は何なのでしょうか?
コーヒーの酸味に影響を与える要素は?
焙煎度合いで酸味は変わる?|酸味を操る焙煎の魔法
コーヒーの味が、豆を「どれくらい煎るか」で大きく変わることはご存じですよね。
この「どれくらい煎るか」というのが焙煎度合いで、コーヒーの酸味をコントロールできます。
焙煎度合いと酸味の関係
コーヒー豆は、熱を加える(焙煎する)ことで、豆の中の成分が化学変化を起こします。
この変化の過程で、酸の量が減ったり、別の種類の酸に変わったりするんです。
浅煎り(ライトロースト、シナモンローストなど)
豆を軽く煎った状態。豆の色は薄茶色です。
この焙煎度合いだと、コーヒー豆が元々持っている酸味や香りが一番強く感じられます。
クエン酸やリンゴ酸といった、さわやかで心地よい酸味が残ることが多いです。
中煎り(ミディアムロースト、ハイローストなど)
浅煎りよりも少し深く煎った状態。豆の色はこげ茶色に近づきます。
酸味は残りつつも、苦味やコクとのバランスが取れてきます。
バランスが良いので、ブレンドコーヒーによく使われる焙煎度合いです。
深煎り(シティロースト、フルシティロースト、フレンチロースト、イタリアンローストなど)
かなり深く煎った状態。豆の色は真っ黒に近いです。
この焙煎度合いになると、ほとんどの酸が熱によって分解されてしまうため、酸味はかなり弱くなり、代わりに強い苦味やコクが強調されます。
エスプレッソや、苦味が好きな人向けのコーヒーによく使われます。
焙煎で酸味が消える仕組み
コーヒー焙煎の一般的な温度は生豆投入時のドラム内温度が160〜190℃程度で、豆の内部温度が100℃を超えると本格的な焙煎が始まり、炒り上がり温度は170〜200℃程度が目安となります。
この焙煎の過程で、コーヒー豆の中の有機酸は熱によって少しずつ分解されたり、別の物質に変化したりします。
特に、焙煎が進むにつれてクロロゲン酸という酸が減少し、その代わりにキナ酸やカフェ酸など、苦味や香りの成分が増えていきます。
クロロゲン酸 → キナ酸 + カフェ酸
そのため、「酸っぱいコーヒーが苦手だな」と感じたら、深煎りの豆を選んでみましょう。
逆に「あまり苦くないフルーティーなコーヒーが好き!」という人は、浅煎りの豆を試してみると、新しい発見がありますよ。
焙煎が進むにつれて有機酸が分解されたり別の物質に変化したりすることで、酸味が抑えられ、苦味やコクが増していきます。
抽出方法で酸味は変わる?|淹れ方が酸味に与える影響
コーヒーの酸味は、豆の種類や焙煎度合いで決まるだけじゃないんです。
実は、私たちがコーヒーを淹れるときの抽出方法や、その淹れ方のちょっとした違いでも、酸味の感じ方が大きく変わることがあります。
お湯の温度が酸味に与える影響
コーヒーを淹れるとき、お湯の温度は重要です。
低い温度のお湯(80℃くらい)
低い温度のお湯で抽出すると、コーヒー豆に含まれる酸味成分が溶け出しやすくなると言われています。
一方で、苦味やコクの成分は溶け出しにくい傾向があります。
酸味が強く感じられやすいコーヒーになることが多いです。
高い温度のお湯(90℃~95℃くらい)
高い温度のお湯で抽出すると、酸味成分だけでなく、苦味やコク、香りの成分もバランス良く溶け出しやすくなる。
一般的に、まろやかでバランスの取れた酸味になることが多いです。
コーヒーの風味を最大限に引き出すには、このくらいの温度が適していると言われています。
抽出時間や挽き目も関係あり!
他にも、こんな要素が酸味の感じ方に影響します。
抽出時間
お湯がコーヒーの粉に触れている時間が長いほど、より多くの成分が溶け出します。
抽出時間が短すぎると、酸味だけが十分に溶け出し、苦味や甘みが足りずに「未熟な酸味」に感じられることがあります。
逆に長すぎると、不必要な雑味やエグみまで抽出されてしまいます。
その結果、酸味がぼやけたり、不快な苦味に変わったりすることもあります。
豆の挽き目(粉の細かさ)
コーヒー豆を細かく挽くと、お湯と触れる面積が増えるため、成分が早く溶け出します。
細かく挽きすぎると、必要以上に酸味や苦味が出てしまって、味が濃すぎたり、不快な酸味に感じられたりすることがあります。
逆に粗すぎると、成分が十分に溶け出さず、味が薄く、酸味だけが目立つこともあります。
つまり、同じコーヒー豆でも、お湯の温度、抽出時間、挽き目を調整するだけで、酸味の感じ方がガラッと変わります。
もし「このコーヒー、ちょっと酸っぱいな」と感じたら、お湯の温度を少し上げてみたり、挽き目を少し細かくしてみたりすると、酸っぱさがおさまるかもしれないですね。
酸味と苦味の相乗効果|コーヒーの奥深さを知る
コーヒーって、酸味と苦味の2つの要素が特に強く感じられる飲み物ですよね。
「酸味と苦味って、なんか正反対の味じゃない?」って思うかもしれないですが、実はこの2つはコーヒーの味わいを深めるために、お互いを引き立て合う、すごく大切な関係にあるんです。
まさに、「相乗効果」というわけです。
なぜ酸味と苦味が共存するの?
酸味と苦味が共存する理由は、コーヒー豆に含まれる様々な成分が、焙煎や抽出の過程で複雑に変化するからです。
- 前にも話した「クロロゲン酸」は、生豆のときは酸味のもとだけど、焙煎されると分解されて、苦味成分のもとになったりする。だから、焙煎が浅いと酸味が強く、深くなると苦味が強くなる。
- コーヒーの中には、酸味と苦味の両方の特性を持つ「キナ酸」のような成分も含まれている。これが、コーヒーの複雑な味わいを作り出している。
つまり、コーヒーの酸味と苦味は、単独で存在するのではなく、お互いに影響し合って風味を作り出しています。
片方だけでは成り立たない、大切な関係ですね。
この酸味と苦味のバランスを感じられるようになると、コーヒーの味がぐっと奥深く、面白くなること間違いなしです。
まとめ|酸味の化学を理解して、自分の好きな味のコーヒーを楽しもう!
ここまで、コーヒーに含まれる酸味の成分や、酸味の少ないコーヒーを飲む方法など、解説してきました。
本記事のまとめです。
・コーヒーには、有機酸が何種類も含まれている。
・焙煎時間が酸味に影響する:クロロゲン酸は、焙煎過程で熱分解してキナ酸やカフェ酸に変化
・抽出方法が酸味に影響する:お湯の温度や抽出時間により、抽出される酸味や苦味の成分が変化
化学を理解することによって、自分にとって理想的なコーヒーが淹れられるかもしれませんね。
参考文献
- 中林 敏郎:「焙煎によるコーヒーの有機酸とpHの変化」日本食品工業学会誌,第25巻, 第3号(1978)
- 小野 善弘: 「コーヒーの科学 ―「おいしさ」を測る」 講談社ブルーバックス(2016)